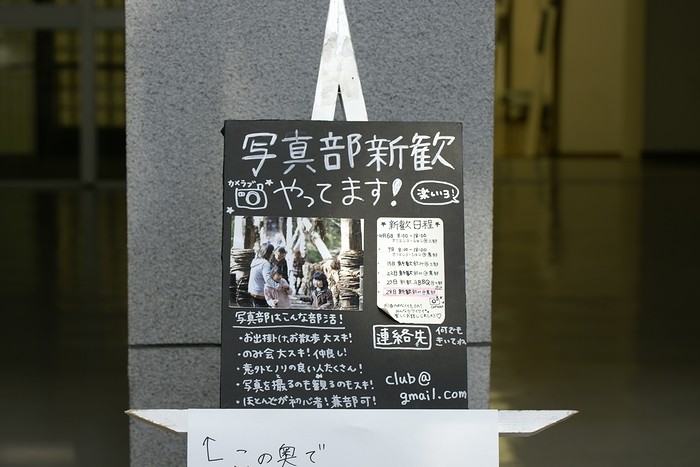数日前に学会発表が終わりました。最近は相当に疲労が激しいのですが、それでも、自分にとってそれなりに意味のある発表にはなったと思います。ただ、聴いてくれていた人びとからは「(壇上で)やけに動き回っていた」「ドスが効いていた」「瞳孔が開いていた」などと、発表内容とは関係のないコメントばかりもらいました。
本当は、知的に眼鏡をくいくいとさせながら、理詰めで隙のない論述を淀みなく語りたいのです。けれども現実的には服もぼろっちく髪はぼさぼさ、ついつい興奮してクマのようにうろうろと歩き回り、時折よだれをたらして唸り声をあげつつ鮭を素手で捕まえる。そんな発表ばかりしています。いやさすがに会場に鮭はいなかったけれど。
今回の発表(そしてここ最近の研究)は「死」がテーマです。いえ、もともと博論を書いていたときからそれは隠れたテーマだったのですが、最近ようやく、自分の書きたいように書いてやれ、と思えるようになってきました。ですので、これからしばらくは、真正面から「死」について考えていこうと思っています。「死」それ自体が目的というより、むしろそこから必然として導かれる見知らぬきみとの原初的な共同性こそが目的だというべきかもしれません。
少し話が変わるようですが、ぼくは研究室のほとんどのひとに、このブログのことを知らせていません。もちろん、興味もないブログのことなど、教えられても却って迷惑なだけでしょう。
ただ、そういったことだけではなく、このブログにおいて、ぼくは父の、そしてあるいは別の誰かの死について幾度か書いてきました。それは現実に起きたことというより(そういった側面が逃れようもなくあるにせよ)、このブログのタイトルがまさに「物語」であるように、そのひとの、そしてぼくの人生を語りなおし続けるということを意味しています。
そうして、それは論文においても同様です。どのようなフォーマットを用いるにせよ、言葉以外のどのような表現によるにせよ、あるいはただ道を歩き、呼吸をし、太陽の眩しさに目を眇めるだけであるにせよ、そのようなすべての経路を通じて、誰もが、そのひとにしか語れないかたちで、あるひとつの(けれど無限の様態を持った)物語を物語っています。
とはいえ、やはり、論文は論文であり、ブログはブログです。当然ですが、ぼくは論文に、ぼくが経験してきた幾人かの死について、直接的に書いたりは決してしません。ブログで(やれないことを承知で)やろうとしていることは、要するに、『ピギー・スニードを救う話』でアーヴィングが語っていることです。そこには避けがたく、(物語として)このぼくの経験としての死が現われます。また、それ以外に書くべきなにものもありません。
だけれども、ぼくは自分が書く論文を、いかなる意味においても私的なものとしては読んでもらいたくないのです。いうもの恥ずかしい話ですが、何らかのかたちで自分の経験を正当性の根拠とするようなものは、それは論文ではありません。それが例え隠しようもなく顕れるものだとしても。
そう、それはどうしようもないものとして顕れてしまうのであって、意図的に表現するようなものでも、完全に消し去れるようなものでもない。そのどちらも、魂を込めた、他にどうしようもないからせざるを得なかったものとしての研究ではない。ぼくはそう思います。
と、ここまで書いてふと気づいたのですが、これは結局のところ、物語を書くときにぼくが思っていることと、何も違いがないようです。
哲学出身でもないままに思想系の研究室に進んでしまい、いまにして思えば、きっと客観的な評価が欲しかったのかもしれません。ぼくというひとりの人間の私的な背景から切り離された言葉。
けれども、所詮は無理なお話です。この世界のなかで描かれるぼくらの軌跡は、そのまますべて、物語です。唯一のこのぼくが、唯一のきみに語る、その都度唯一のものとしての物語。
だから、もっと自由に論文を書こうと思います。虚実を織り交ぜ、このぼくという位置からあふれ出す、あることないこと、ないことあること、無数の言葉の欠片、無数の欠片の言葉。もっと自由に、もっともっと自由に。
その欠片のたった一葉だけでも、きみの下にある日ひらりと届けば、人生なんて、それで大成功。