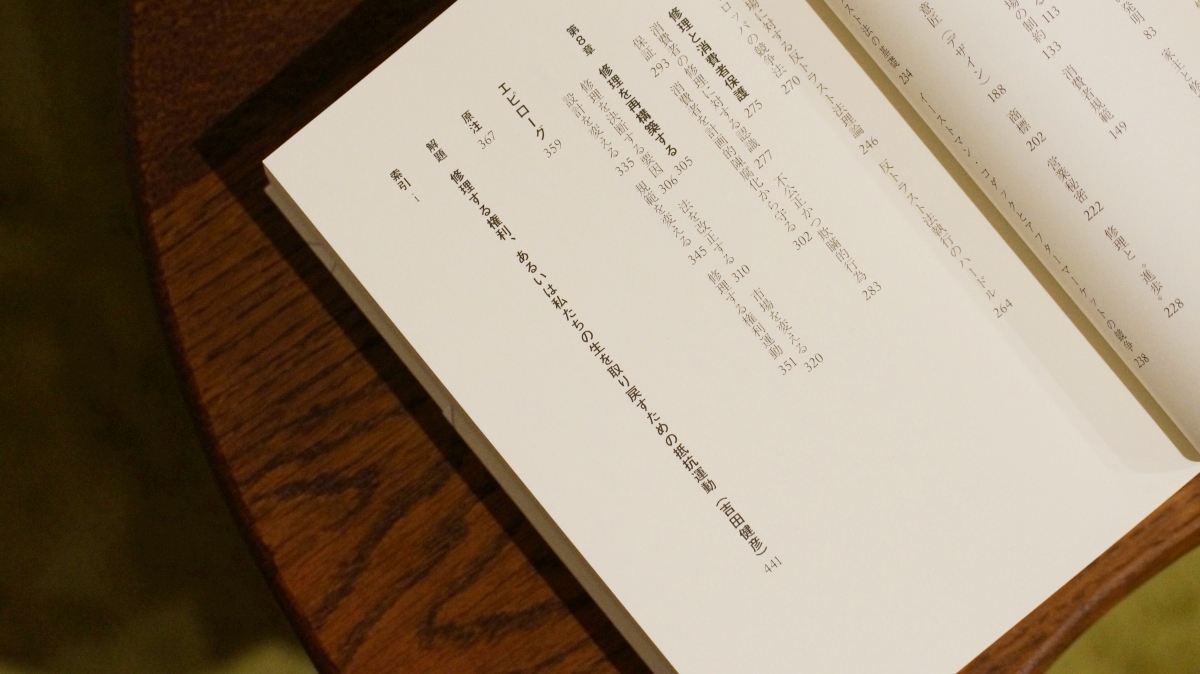早稲田大学教育学部の入試で『メディオーム』が出題されました。ぼく自身はいまの大学制度にあまり賛同していなくて、とは言っても、かつて良かった時代があった訳でもなく、所詮は相対的なもの、個人的な感覚によるだけでしかないのでしょう。それにそもそもぼくは最初にいった大学を中退しているので、良いも悪いも判断できる立場ではないのかもしれません。
とはいえ、大学で学ぶということがもっと自由であるべきなのは、どのような状況においてもそうであってほしいと願っています。入学試験は確かに必要な面もありますが、大学の自由さを前提とした形に少しでも変えられないだろうかと思います。
そういった意味では、入試に自著が使われたのは、読んでくれているひとがいると分かってとても嬉しい反面、それよりも自由に読んでもらえるといいな、でもできればゼミとかで使ってもらえるとさらにいいな、そしてたくさん売れると良いな、などとも思います。漏れる本音。
それはそれとして、一つだけこれは書いておかないとなと思ったことがありました。代ゼミで出している解答速報に対するものです。
まず初めに前提としなければならないのは、これはあくまで「解答例」だと書かれているということ。とはいえ一般的な受験者であればこれが正答だと思ってしまうでしょう。そして第二に、そもそもこれは『メディオーム』全文を読んだうえでの解答が求められているのではなく、出題部分のみから判断しなければならないということ。あるパーツだけ切り取れば、全体とはまったく異なる方向性を持っているものなど幾らでもあります。だから、試験問題に対する解答としてこれが正しいかどうかはぼくには判断できません。いやできるだろうけれどそこまでの気力が湧きません。
+
要するにこれはゲームです。しかも、ただルールを適用すれば答えが出てくるような。それはぼくはあまり興味がないのです。別段、それは人間性に対して何か答えを出せるようなものではない。いままさに受験をしている人からすればそんなことを言っている余裕はないでしょう。だからそれは無責任に言っているのではなくて……でもやっぱりたかがゲームだという視点は持っておいた方が良い。失敗したって、とにかく生きていれば何とかなるし、何とかならないとしたらそれはその人のせいではない。
ぼくは小さいころからそういうゲームを、というよりもゲームをそのようにしか捉えられない大人を莫迦にしていました。嫌な子どもだな。でもゲームって、例えばコンピューターでもプレイできる、そういったものだけではありません。話がずれますが(とはいえそもそも話がずれていくのがぼくのスタイルなのでそれはもう仕方がない)、いまはやりのAIとか、すぐに「チェスが、将棋が、囲碁が」とか言い出すひとがいるけれど、もっとも早く人間に勝てるようになったチェスでさえ、そういった人たちが言っているのは実際にはチェスでも何でもない、ただの計算の話でしかありません。もちろん、ただの計算だって物凄いことです。でもそれは電卓で「1 + 1」の答えを出せるのと同じ意味でのみ、奇跡的であり途轍もない偉業だということなのです。ゲームの本質はそれとはまったく別のところにあります。以下は以前に引用したことがありますが、とても重要なので改めて。
「ヴァンス、あんたはどうして分隊の仲間とチェスをしないんだ。弱すぎて相手にならないからか」長い沈黙。またヘマをやってしまった。これも、首をつっこむべきことじゃなかったようだ。ヴァンスは立っており、ぼくは穴の底にしゃがんでいる。彼が見下ろす。「人に言わないなら」「ファーザー・マンディの名誉にかけて約束する」彼は闇に目をこらす。「おもしろくないからだよ。勝ってしまうからじゃなく、みんながチェスをしてないからだ。あれでは遊びにならない」黙っている。「ドイツ語ではチェスを『シャック』というんだ。彼らの言葉でいう戦闘[シュラクト]に語感がよく似ている。ミラーも他の連中もそうだが、チェスを闘いだと思っている。そうじゃなく、チェスは誘惑なんだ。クイーンがキングを誘惑しようとするゲームだよ。キングの抵抗力をなくして誘いだす。そういう遊びであって、あれには勝ち負けなどないのさ。追いつめたときに『チェックメイト』というだろう。殺すのでも捕まえるでもなく、最終的には縁組み[メイト]するものだ。そう考えれば、誰でもチェスで遊べるようになる」
ウィリアム・ウォートン『クリスマスを贈ります』雨沢泰訳、新潮文庫、1992年、pp.137-138
これがゲームだとぼくは思います。まあそれとは関係なしに『クリスマスを贈ります』は本当に名著なのでぜひお読みください。
+
で、話が戻りますが、いや戻りそうで戻らないのですが、なぜぼくがこんな曲がりくねった構造で書くかといえばそれがぼくの思考のスタイルだからです。それはやっぱり学会に投稿するような査読付き論文には合わないし(それこそ書こうと思えば書けますが、結局それもルールで解けるゲームでしょう)、学会発表とかにも合いません。けれどもぼくはそういったグダグダした大量の言葉こそが世界を生み出すのだと思うし、そういった無数の言葉によって作り出された流れのようなもの、その全体でしか、ある本が伝えたいことは伝えられないと思うのです。そうでないのなら、そんなものはAIにでも要約させれば良いのだから。書くのも悍ましいですが100分で名著がどうしたこうしたとか、まあそんなものです。
+
だから、機械にも解ける試験問題のことではなく、あくまで本の話として、代ゼミの出している解答例、特に問一の解答は、あの本で描こうとしていた世界観からまったくかけ離れたものだと言わざるを得ないのです。繰り返しますが、あくまで本の話です。そこでは答えとして次のような選択肢が選ばれています。
「メディア技術の進展が不可避的に増殖させてしまう感情や憎悪を、確信を持って乗り越えることができる理性的な個人を育てていく必要がある。」
これはぼくの考えとはまったく真逆です。そもそも『メディ』の出発点にあるのは、理念としての理性的人間の不可能性と欺瞞なのです。そして「この私」単独で存在するような(そもそも「確信」だって「この私」を無条件に信じているからこそ可能な訳ですが)主体的個人という概念に対する根本的な批判です。
そうではなく、まず他者が在る。その他者からの呼びかけによって、どうしようもなく応答を強要されるものとしての私が生まれる。この私の始原には常に私ではない他者が在り続ける。それは途轍もない恐怖であるが故に、原理的に他者が必要であるにもかかわらず私は他者を遠ざけ、あるいはコントロール可能なリソースと見做すようになる。その避けがたい引き裂かれから、感情が、文化が、テクノロジーが、要するに生が生まれてくる。『メディオーム』ってそういう内容なんです。あれ、これ伝わりますかね……? いや伝わらなくたって良いのです。だからこそ対話が、あるいは葛藤が生まれるのだから。あるいは、だからこそ本を買ってもらえるのかもしれないから。ぜひ買って欲しい。もうね、一家に一冊どころか一人三冊ですよ。
ですので、この選択肢、「確信」、「乗り越える」、「できる」、「理性的」、「個人」、「育てていく」、「必要」、すべてに引っ掛ります。そうではない人間の存在原理があるとして、なおぼくらは民主主義を考え得るのか。考え得る、というよりいもそうせざるを得ないというのがぼくの思想で、だから政治や制度的なものとしてではなく、根源的民主性といったりします。
とはいえ、誰かが突然「すべてに先行する他者が……」とか「絶対的な畏怖と恐怖をベースにした民主主義が……」とか日常会話で言い始めたらちょっと怖いですよね。だからこそ本という形式をとることが必要なのです。ゆっくり、読む人のペースで、誰かの書いた世界について考えることができる。ぼく自身は近代的個人というものについては批判的ですが、急にそんなことを言っても意味が無くて、悪くすれば、何かこう人権とか無視しても良いじゃんとか思っているひとに思われてしまいかねない。そうではまったくないのです。もし時間に制限があるのなら、ぼくも近代的個人をベースに話したり書いたりします。それは嘘とか誤魔化しではまったくなくて、それでも絶対にその人のスタイルは出るはずなのです。そしてもしそこで興味を持ってもらえれば、『メディ』を買ってほし[以下略]。
ぼくがバトラーやナンシー、リンギス、あるいはレヴィナスに惹かれるのは、そしてレヴィナスはちょっとアレですがバトラーやナンシー、そしてリンギスを尊敬するのは、他者に対する絶対的な畏怖を原理として民主主義を考えているからです。これは、まず私が在ることを前提して他者を尊重するということとはまったく異なります。ぼくがハーバーマスを尊敬しつつ思想的には同意できないのは、ハーバーマスの間主観性には本質的に他者との断絶や恐怖が位置づけられないからです。とはいえ、彼の場合は規範倫理だからこれは批判というよりも立ち位置の違いというだけで、彼が本物の哲学者であることは間違いありません。
けれども、そうしようと思うぼくらの在り方にもし力を与えられるとすれば、それは恐らく理性ではなく、あるいは理性であってもその根底に横たわる、異様なまでの狂気にも似た、この引き裂かれだとぼくは思うのです。例えばサン・テグジュペリが沙漠で遭難したときの「我慢しろ……ぼくらが駆けつけてやる!……ぼくらのほうから駆けつけてやる! ぼくらこそは救援隊だ!」(サン=テグジュペリ『人間の土地』堀口大學訳、新潮文庫、p.144)という言葉、この異様な迫力。ぼくはここにもやはり狂気のレベルにまで高められた人間の崇高さを見出します。それは人間にのみ可能なもので、けれども別段、それ故他の生き物より優れているものではなく、単なる特性であり、苦痛でしかありません。それでもやはり、そうであってもやはり、あるいはどうしようもなくやはり、ぼくらはそこからしか始めることができないし、だからもし民主主義というものがほんとうにあるのだとすれば、それはイデオロギーの論争みたいなものではなく人間の原理でしかないのだと……。まあでも、要するに物語です。つまらなければ本を閉じれば良い。それでもなお、物語には途轍もない力があるはずです。
+
後期の非常勤が始まったばかりのころ、大学の正門を通って並木道を歩いていたら、小さい小さい、カメのような石がありました。何だか可愛いなと思いながら通り過ぎ、ふと気になり戻ってよくよく見れば、それは本物の子ガメで、既に死んでからある程度経ち石のように硬くなってしまったものでした。ぼくはいまだに倫理の授業をするということの意味がいまひとつ分かっていません。教科書を読めば分かることは教科書を読めば分かります。ルールがあるのならそれに沿って解けば良いだけです。そんなことよりも、誰もが足もとを見て歩いた方が……。
それは決してナイーヴな何かではありません。象徴的な、ということでさえありません。それがどこに向うか、何を契機として向うかはそれぞれに違うでしょう。かつてぼくは、神との闘争、しかも存在しない神との闘争という訳の分からないものへと突き進んでいきました。他のひとには、その人なりの道があるでしょう。
非常勤の講義はプログラミングの時間を削って引き受けているので、金銭的にはかなりのダメージになりますし、仕事先の評価的にもデメリットばかりです。けれどもいちばん大きいのは、成績をつけることによる精神的なダメージです。意味が分からない。機械でも処理できるゲームの結果を採点しているのでしょうか。そうなのかもしれません。けれども、本来はそうではないはずです。考えること自体があれば、もうそれだけで良いのだとぼくは思います。
+
子ガメの話を彼女にした日の夜中、ふいに彼女が、でもきっと兄弟がたくさんいるよ、と言いました。ほんとうにそうだといいねえ、とぼくも応えました。