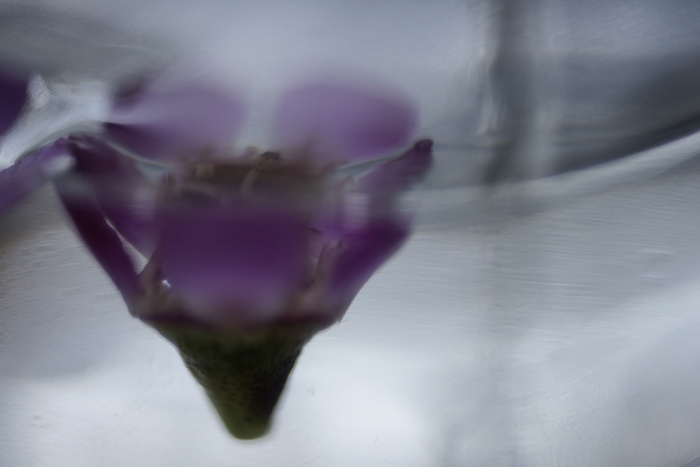昨日、相棒とふたりで、ひさしぶりに彼女の地元を歩いた。ほんの二、三年行っていなかった場所を歩いてみると、ぼくらの頭のなかにあった地図はすべて古くなっていた。ものごとというのは、大抵の場合悪い方向へと転がっていく。けれども無限音階のようなもので、悪くなり続けつつ、いつまでたっても底に辿りつかず、現在に留まっていたりもする。何となく漠然としんどさが続き、へとへとになっても終わりは見えてこない。それでも、ふと気づくとぼくの服の上をしゃくとりむしがえっちらおっちら這っていたり、道の脇を唐突にカモのつがいがよちよち歩いていたり、そういったものに触れて、強ばっていた心が和らいだりもする。昨日は今年になって初めて天道虫を見つけた。クロアゲハが飛び、雨が近づけばアマガエルが鳴き、そして、そうだ、最近では、これはぼくの地元だけれども、夜通しふくろうが鳴いたりもする。散歩に出かけ、夜もうるさい車通りを離れ、真暗ななかに立って彼女にPHSをかける。小さな森のなかから届くふくろうの声を、彼女に届けたりする。
* * *
あるとき、ふと、眼の前に小さな惑星が浮かんでいた。サン・テグジュペリが好きだというから何がと訊くと星の王子さましか読んでいないような連中がぼくはほんとうに嫌だ。けれども、無論、星の王子さま自体が嫌いなわけではない。むしろ逆だ。ともかく、あれをイメージしてもらえれば近いかもしれない。小さな惑星の上には、縮尺的につりあわないくらい大きなビルが林立している。林立といっても、惑星の表面自体が狭いものだから、せいぜい数十といったところだろう。そうして、そのひとつひとつに、ちょっとうまく説明できないのだけれど、ぼくの心のなかにある感情のひとつひとつが対応していた。眼の前に浮かんだ惑星のうえで、いちばん大きく建っていたのは(ただし聳える、という感じではなかった。それはひどく精細でありながらも、ミニチュアの可愛らしさを持っていたから)「死にたい」という名前のビルだった。しばらくそれを眺めて、瞬きをしたら消えていた。
こういうことを書くと、何だかネガティブだなあ、とか、こいつ大丈夫かなあ、とか思われるかもしれない。あるいは、よく分からないけれども格好つけ、とか。だけれど、そういうことではない。それは単にそれだけのことで、たいして意味があるわけでもない。むしろそういった感情がありつつ、どうして生きているのかというほうにこそ、ぼくは意味があると思うし、関心もある。ただぼんやりと生きていて、それが生きていることなのなら、いうまでもなく、別段、ぼくらは生を問う必要などない。それはそれで幸福なのかもしれないけれど、そうであるのなら、これもまた、ぼくらは幸福を問う必要などない。
「死にたい」というと、何だか変な前提や変な思い込みや変な押しつけをされてしまい、話ができなくなる。それは面倒くさいので、適当にお話を作り、適当にお話をする。何だかマッチョなひとたちだなあ、と、ぼんやり思う。そのマッチョさというのは、要するに、おしるこ万才の持つ鈍感さ、愚鈍さだ。ぼくはそれを嫌悪する。
* * *
奇妙な――といってもそれほど奇妙な話でもないけれど――ものが見えるということであれば、最近、もうひとつあった。会社でパソコンのモニタを眺めていたら、ふとコーディング中のプログラムの向こうに、その文字列を押しのけるように、とある景色が現れた。これもまた正確には表現できないのだけれど、それは、ぼくが知っていたあるご老人の、そのひとがまだ若かったころによく眺めていた光景だった。その老人は既に亡くなっているし、生前、そのひとからぼくがその光景について聴いたこともなかった。それでも、ぼくには「分かった」。それがいわゆる事実かどうかということでいえば、無論、答えるのも阿呆らしい。でもそれは、事実ではないという当たり前すぎることだから阿呆らしいのではない。問うべき軸がずれすぎていて、阿呆らしいということだ。
しばらくその光景を眺めてから、キーボードを叩き、それを消した。
* * *
この社会(どの社会?)が持つ残酷さというものがある。そしてぼくはぼくなりの残酷さを持って、自分にとって嫌悪すべきものを嫌悪する。その残酷さのベクトルが異なっているから、ぼくはぼくなりにシステムに妥協して生きていけるし、システムもシステムなりに妥協して、ぼくのような存在を――何らかの使い道がある限りにおいて――見逃している。システムには無数の、ぼくとは異なるという意味においてぼくと似ている誰かさんたちがもぐりこんでいる。ぽこぽこぽこぽこ、偶発的に必然的にシステムの内部で生まれつつ、ぽろぽろぽろぽろ、システムにとっての有用性を失って虚空へと捨てられていく。それは例外的存在などではなくて、そういったヴィジョンそのものに、あるいはそこのみに、この世界のリアルさがあるとぼくは思っている。