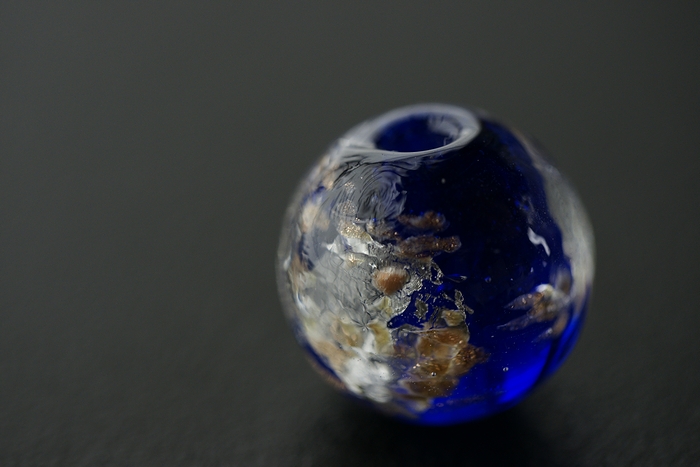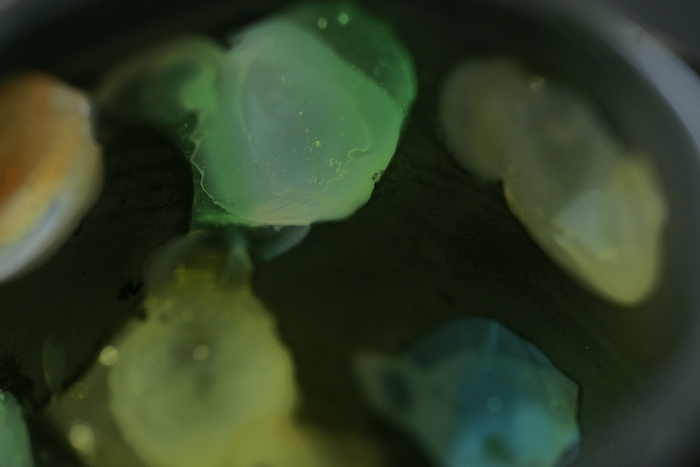学会発表が終わり、これでことしの研究活動はとりあえず一区切りです。もちろん、一区切りというのはあくまで外的なスケジュールとしてはということで、研究そのものはいつでもいつまでも続いていきます。まともなプログラマなら誰でもそうだと思いますが(どう表現するかはそれぞれでしょうが)、頭のなかに一つの臓器を作り出して、それは心臓のようにいつでも眠っているあいだでも止まることなくアルゴリズムを組み続けています。その臓器に焼きつけたロジックを何度もなぞり直し、呼吸のようにバグがないかどうかをチェックし続けています。心臓の動きが不随意であるように、それはもうぼくには止めようのないものです。研究も同じです。頭のなかに独立した臓器を作り出す。研究臓器。どくどくどくどく、薄気味悪くけれど避けようもなく、それは何かを齧り続け吐き出し続けています。しかしそれらは同時に動くことはできません。仕事と研究。頭のなかに切り替えスイッチを思い浮かべて、そのスイッチを指で軽く弾きます。ぱちん。いまからぼくは研究頭。もちろん、もちろん、そんなこと、できるはずもありません。それは、つまらない話ですが、気が狂いそうになるほどの苦痛です。「仕事と研究の両立をしているなんて偉いね」と言われてそれはそれでありがとうと思うのですが、現実はそんなに良いお話でもありません。他人の0.6の能力しかないぼくが仕事と研究の双方をしようと思えば、オーバーヘッドの部分を除いておそらく0.2と0.2くらいしか成果を出せない。しかし出せないというのはただの私的な言い訳に過ぎないのでそんなことはおくびにもださず、吐き気がするほどすがすがしく罪悪感の欠片もない嘘によって片足立ちのまますり抜けていきます。とはいえしかし、そうはいってもそれにしても、やはりそれは気が狂いそうな苦痛です。最後は叫びながらへらへらへらへら笑いながら論文を書いたりします。存在しないスイッチを切り替えようと無理やり脳のどこかに指をねじ込むと指が折れたりします。ぼくはいったいどこに何を突っ込んでいたのか。ぶらぶらする指を眺めつつしばし呆然とします。呆然としつつ、明日はふつうに会社です。学会の雑務も山のように残っています。スイッチを切り替えすぎて、何だかどこからか焼け焦げた匂いがしてきます。それでも、講義のコメントシートに、先生のお話は面白いですなどと書かれているのを読むと、頼むから俺のような屑を先生と呼ばないでくれ俺は人間としての屑の極北に在ることに誇りを持っているんだと胸を抉るようにつかみつつごろごろ転げまわりつつ、それでもやはり嬉しかったりします。学会発表面白かったよと言われれば、夜中にげろを吐きつつ口からは出さず気合で飲み込んだりすつつ少しばかり無理をして良かったと思ったりもします。
生きている限り、ぼくらはつねに生きなければなりません。それは死者に対するぼくらの義務であり、生きる苦痛のなかでのみ死者とつながれるという意味においてそれはエクスタシーをぼくらにもたらします。苦しければ苦しいほど、そこには確かに何かがあります。表現できない何か。だけれども、だからこそ、ぼくらは目を閉じたまま、言葉を発しないまま、それに触れ、撫でまわし、漠然とその総体を想像したりします。それはきっと、死んだ後にぼくらの目の前に現れ、あり得ない解像度で見えるナニモノカの予兆でしょう。でもとりあえずは、生きている限りにおいて、走り続けなければなりません。
明後日には、執筆者の片隅に混ぜてもらった書籍が書店に並ぶそうです。出版社から直接購入する場合には著者割引というのがあるそうなのですが、なんとなく、一冊、書店でこっそりひっそり定価で購入し、いまはもういない誰かさんたちとともに、ささやかにお祝いをしようと思っています。