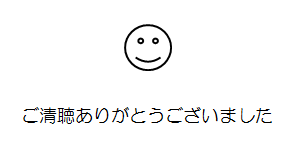最近急に書かなくてはならない原稿が増え、いま、今年中に書かなくてはならない原稿が5本あります。結局のところぼくらは業績でしか評価されないという面もあり、そういった意味ではありがたい話なのですが、それでも、あまりにひどいテーマで執筆依頼が来ると、書かせてもらえるなんてありがたやありがたやと土下座しながら小躍りしつつ、同時に憂鬱な気持ちになってきます。とはいえ、もともと嘘と言い逃れとその場しのぎだけを友だちにして生きてきたので、恥ずべき糞のようなテーマであっても、何かしら自分なりに抜け道を組み込んで書くことができるのではないかと、何となく能天気に自分を信頼したりもしています。
それとは別に、同人誌のお誘いを受けたり、研究仲間から(まだどんな形になるのかは分かりませんが)共著本を書こうよというお誘いを受けたり、それはそれで大変なのは分かり切っているのですが、でも、とても楽しい大変さです。前者には、名づける者に対して名づけかえす復讐の物語を、後者には、ベンヤミンとバルトの写真論を引きつつ、現代のLifelogを分析するみたいなことを書こうかと思っています。もっとも、恐らく、どちらもいつも通り、最終的には当初の予想とはまったく異なるものになるのでしょうが。
人間、無理をすると、成長なんてしませんね。いや成長するひともいるのかもしれないけれど、普通はしないんじゃないでしょうか。ぼくが弱すぎるだけでしょうか。ぼくもそこそこ長くは生きていますので、それなりにそれなりの無理は経験してきました。そうして、そういった体験によってどうなったかというと、自分の持っている可能性や力といったものが容赦なく削り落とされてしまうだけでした。それは老いるとかなんとかではなくて、純粋に、システムが人間に対して働く暴力です。そうして、システムは人間の欲望の延長線上に生みだされたものでもあります。
でもまあ、何だって良いんです。どうせどんな時代に生きていたって、そういった暴力のなかでぼくらは生きざるを得ないのですから。諦めているわけでも、そういったなかでも生き残る俺マッチョ、と誇るわけでもなく、単に、ぼくらがどうしようもなくあがいているという事実があるだけです。ぼくの視線は、つねにそのあがいている姿それ自体に向いてしまいます。システムがどうとか、どうも、あまりそういうことを考えるのには向いていないようです。
ぼくの場合は、いろいろなものが削ぎ落とされ、なおあがくその姿は、何かを書く、書き続けるということにおいて現れます。正直、論文なんていくら書いたって職にありつけるわけでもなし、職にありつくことが目的でもなし、でもありつけなければ現実問題あと数年で食べることすらできなくなるし、そしてそれは凄まじくシビアな話であるにもかかわらず、やはり、どうでも良いのです。いや良くはないし何とかしなければならないのですが、ある次元においてそれは、ぼくのことでありながらぼくの手を離れてしまっていることでもあります。
ほんとうは、彼女とふたりで、ただ心静かに暮らしたいだけなのです。何千冊という本を読んできたし、とんでもない時間とお金を勉強するためにつぎ込んできたし、でも、そんなことはすべてどぶに捨ててしまったって良いんです。でも、そうはいかないんですよね。生きている誰もがそうであるように、生きている限りにおいて、ぼくもまたあがき続けるしかありません。生きること、在ること、あがくこと。哲学なんて所詮はトートロジーで、それだけで良いんです。
糞のようなテーマの依頼原稿も、出版される可能性のない写真論も、中途半端に神を憎んだ物語も、とにかくぜんぶひっくるめて、文字を刻んでいこうと思います。刻んだぶんだけ前に進めるのなら、誰にも見出されることのない痕跡しか遺せないとしても、それはそれで、十分なのです。