暑い日が続きますね。つねに人体発火状態のぼくは、巨大な保冷剤を身体に押しつけ、暑さのあまり幻覚を見ながら過ごしています。きょうは、初めて買ったペットボトルのお茶に「ヘルボイス・シティ」と書いており、思わずア゛ア゛ォ゛ア゛ォ゛と気分よく歌ってみたのですが、改めて見直せば「ヘルシールイボスティー」でした。そういえば、昔はしばしば熱を出して寝込んでは、どことなく不吉な、暗いオレンジ色をしたゴムの氷嚢を頭の下に敷いて寝ていました。あれでは悪夢以外の何を見るのかという気もしますが、さすがにいまの時代あんな色をした氷嚢はもうないだろうと思いちょっと調べてみたら、ありますね。いまでも定番のようです。まあ、スタイリッシュな氷嚢なんてものがあっても困るしなあ、などと思って念のために調べてみると、これまたありました。スタイリッシュが売りの氷嚢。世界は不思議なもので満ち溢れています。
満ち溢れているといえば、世界は不思議な言葉でも満ち溢れています。きょうはひさしぶりに喫茶店で本を読みながら相棒の仕事が終わるのを待っていたのですが、ぼくの隣の席に女子高生がふたり、座りました。聴くとはなしに耳にはいってくる彼女たちの声を聴いていると、奇妙なことに、ひとりの喋る言葉は普通に聴き取れるのですが、もうひとりの子は、いったい何を喋っているのか、3割程度しか分からないのです。無論、それが良いとか悪いではなく、 ゼネレーションギャップを嘆くわけでもなく、分からないということそれ自体のもつユーモラスな在り方に、思わず内心で笑ってしまうのです。
いうまでもなく、それは相手を莫迦にした笑いではなく、分からなさを通して避けようもなくぼくらに突きつけられるぼくらのリアル、その前で右往左往するぼくら全体が持つ滑稽さに対する笑いです。
コミュニケーション、というと、多くの場合は、分かるということが出発点にあるか、あるいは分かろうとするということが目的にあります。けれどもぼくは、やはり、分からないということを出発点として、そうして、分からないということのただなかに留まり続けるようなコミュニケーションについて考えていきたいのです。分かるということが絶対的な前提であるアカデミズムのなかで、こういったことを扱うのは、けっこう、面倒くさいものです。分からないということが分かる、みたいな中途半端な話に落とし込もうとされますし、実際、その圧力は非常に強いものがあります。けれども、だからこそ、そこで言い続けることの意味もまたあるのだと、ぼくは思います。まあ、どこまで気力が持つかは分かりませんが、分かる分からないで決まるような次元では、どのみち研究なんてものはできるはずもありません。
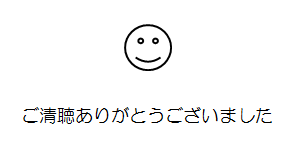
学会で使用したPowerPointの最後は、こんな感じです。分からないことのなかで在り続けるって、ハードで、ハードで、そんでもってハードですよね。けれども同時に、そのハードでしかないぼくらのあがきもがきの全体が持つユーモアを、少しでも伝えられたらいいなあと、そんなことを考えています。
