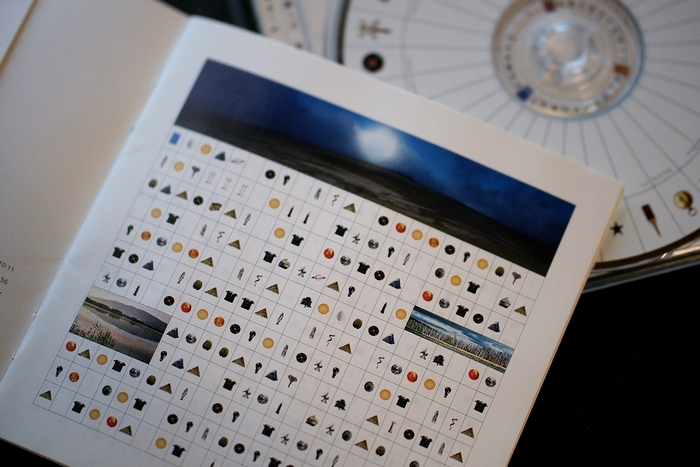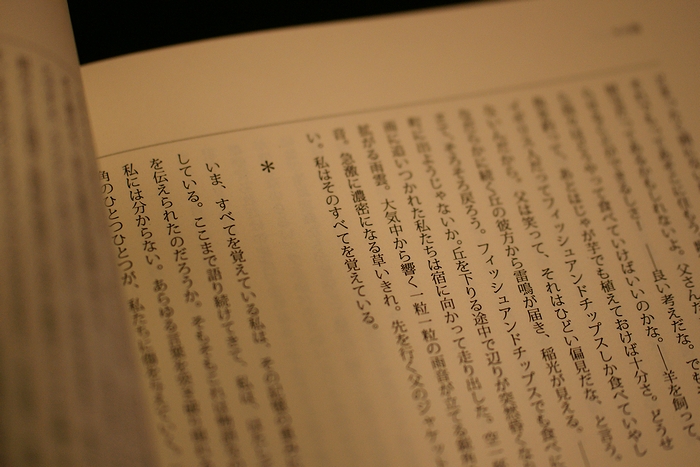まあだいたい、クラウドリーフさんの日常は平々凡々たるものです。特に冒険はない。仕事をして、少し研究をして、歯医者に行って、一週間が終わります。明日からまた月曜日だと思うと憂鬱ですが、なに、ジョバンニに比べればどうということのない日常の戦いです。それでは何も書くことがない。しかし書くことがないから書くことを作る、というのは、極めて下賤なことです。それでは主客が転倒している、いや、そもそもそのとき転倒する「主」などなくなっているので、ただ「客」だけがある。自律し始めた「客」が、ネット上でびくびくと脈打ちながら有機体のようにぬるりと肥大化していく。というのは個人的に好きではないので、歯医者の話をしましょう。
ぼくは、骨格だけは頑丈に生まれつきました。いや子供のころは小さくてまるまるしていたのですが、あるとき突然、巨大化、頑丈化し始めた。アブダクションのおかげですね。アブダクション健康法。ともかく、見た目の骨格構造が頑丈なので誤解をされることが多いのですが、あまり筋力はありません。脚だけは山岳民族なのでどこまでも歩ける筋肉がついていますが、それ以外はもうお留です。いやお留さんって誰だ、乙女です。握力がないのは、便利な器具(缶詰を開けたりするアレとか)でカバーできますが、顎の力がないのには困りものです。
歯医者に行くと、当然、口を開けなくてはなりません。ぱかーっと。これがつらい。そもそも口が大きく開かない。あまり開くと顎が外れそうで怖い。ぼく怖い。ぶるぶる震える巨大な不審人物。でも、がんばって口を開くわけです。ところがあっというまに顎が疲労する。疲労して、ぶるぶる震えだす。先週は、削ったところに詰め物をするために型をとりました。何かこう、生ゴムのようなものを歯に押しつけ、その上から金属のヘラのようなものを当てて、それをぐっと噛む(目を瞑っているので、もしかすると全然違うかもしれない)。固まるまでしばらくはそのまま噛んでいる。歯科技師さんが「ちょっと噛んでいてくださいねー」と言って、どこかに行ってしまう。そうすると、あっというまに顎の疲労がマックスになります。けれども、よりつらい人生を私は生きてきたのです。この程度のこと、耐えられない理由がありましょうか。いやほんとうにこの程度のことなんだよな……。しかし彼は耐えられないのです。疲れて開こうとする顎と、閉じたままにしようとする意志がぶつかり合い、金属のヘラをガチガチガチガチ噛み鳴らすことになります。
「どうですかー」と歯科技師さんが戻ってきます。どうなっているのか、こちらの方が訊きたい! と思いつつ、「ガチガチガチガチ!」と答えます。恥ずかしいので目は閉じたままですが、明らかに歯科技師さんは笑っている。憤激し(しないが)「ガチガチガチガチ!」と主張します。「ではもう良いので、口を開いてくださいねー」と言われますが、もはや筋肉を制御できない。「ガチガチガチガチ!」何か、威嚇をしている新しい生き物のようです。そうだ、俺はアブダクションを受けた結果、新しい生命体になったのだ。しかし鋼鉄の意志が勝ち、口を開けることに成功します。「ガパッ!」0か1かで生きるクラウドリーフさんの潔さが、こんなところにも表れて、好感度がかなりアップです。誰からのでしょうか。きっと宇宙人からのでしょう。
ともかく、彼の日常はこんな感じで過ぎていきます。明日もまた仕事です。電車のなかで読む本がないので、既に絶望モードです。ムンクの叫びに出てくるようなひとの顔をしつつ、世界の叫びから耳を塞いで仕事に向かうしかありません。生きている楽しみですか? そうですね、来週も歯医者に行くことでしょうか。しかしクールなその受け答えも、他のひとが聴けば、ガチガチガチガチ! ギチギチギチギチ! そんな新しい生き物が私です。みなさんはお元気にお過ごしでしょうか? 私はいつも、いつまでも元気です。