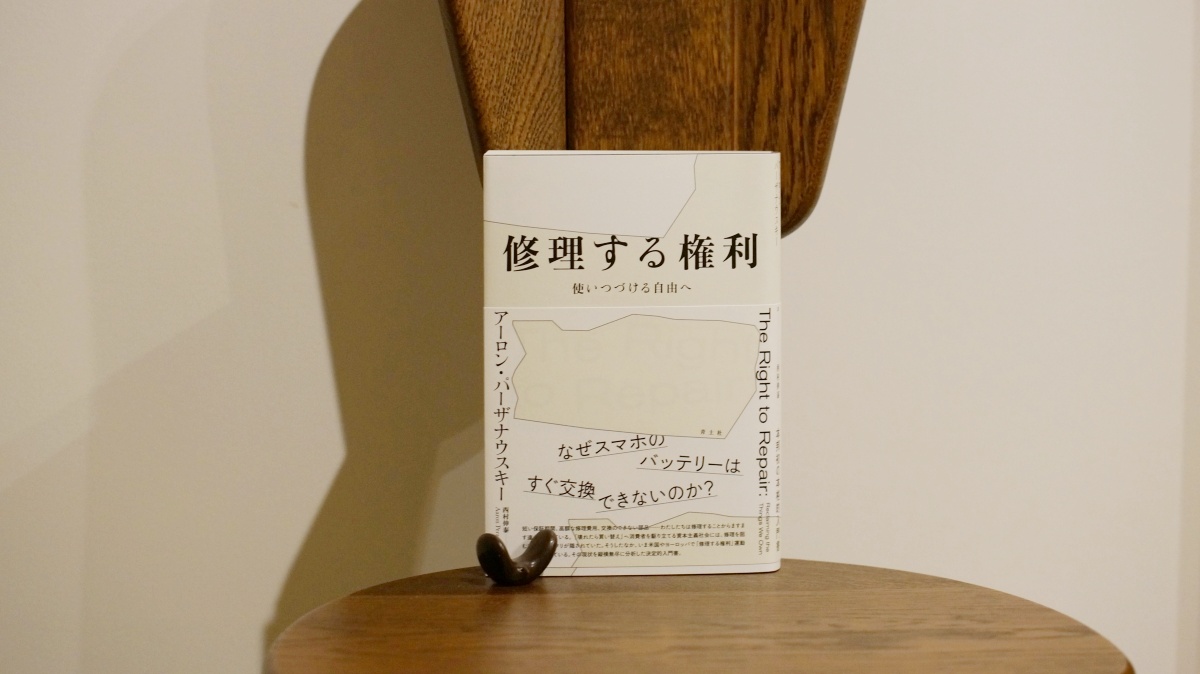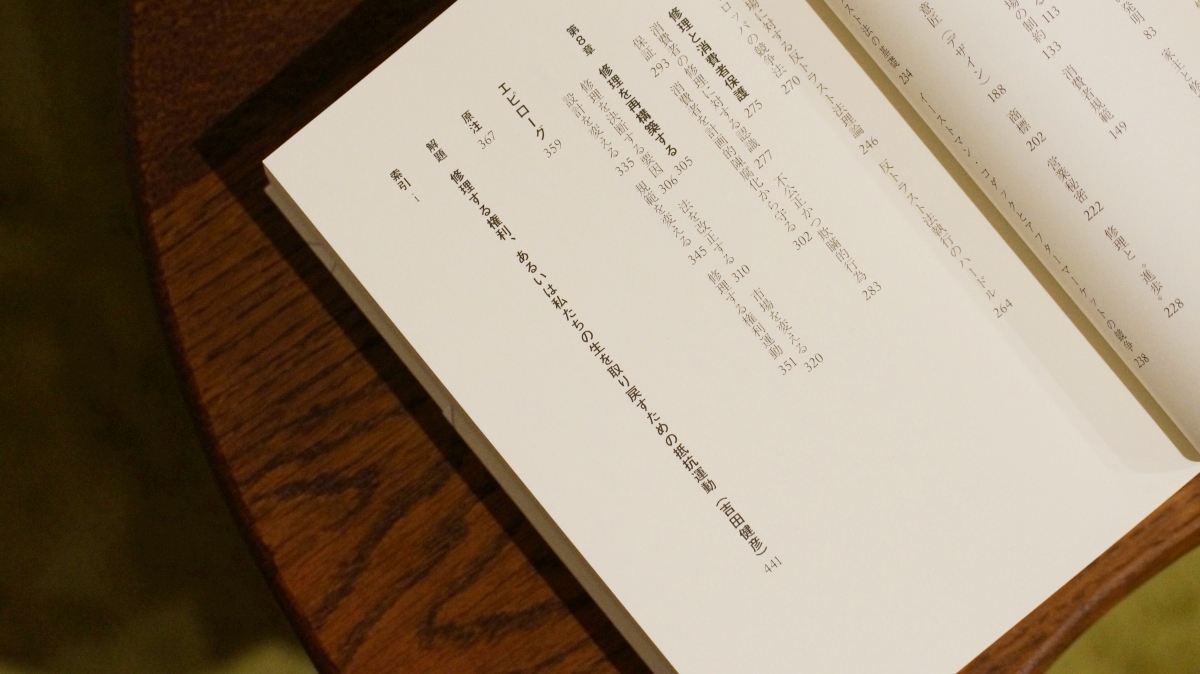会社の決算期が7月なので、9月には納税しなければなりません。複雑怪奇な税務処理は会計士さんにお願いしているのですが、最低限の資料は揃える必要があります。これが難しい。ぼくは別に株式会社を作りたかったわけではなく、ただ契約上の問題で作らざるを得なかっただけなのです。なのにこの仕打ち! いえ別に仕打ちということもないのですが、とにかくこういう作業は苦手です。しばらくは胃が痛く、それでも、とにかく今年も何とか乗り切れました。
同時期、ふたたび定期的に襲ってくるある種の強迫観念に囚われ、最近は頻度は減ってきているのですが一回あたりの強度は高まっており、だいぶ苦しみました。体重もまた減りました。こういうときは頭のなかで常にブザーを鳴らし続けます。思考は細切れになりますが……なりますが……考えてみればどのみちいつも細切れな思考だな。
きょうから後期の講義が始まりました。けれどもひさしぶりに大学構内に侵入しようとすると、結界に弾かれます。これが辛い。なので少し早めに行って大学周辺をぐるぐる回り、反発力の弱いところを探しながら少しずつ入り込んでいきます。
――変質者……。
きょうはガイダンスなので、講義の雰囲気だけを伝えると、あとは逃げるように立ち去りました。でもねえ、大事なことです。担当の非常勤がこういうダメ人間であるということを肌で感じてほしい。そしてできれば、受講を取りやめてほしい。
ああでも、きょうは、ゼミ時代の研究仲間がその大学で教員をしているのですが、少しお邪魔をして『修理する権利』を渡しに行きました。そうしたら代わりに長ネギを二本もらえました。とてもとても立派な長ネギ。古き良き時代の大学を感じられ、にっこりして帰ってきました。こういうことがあると、結界が緩むので助かります。
――だけれども、こんな人間でも、がんばって普通の人間のふりをして生きているんです。ぼくはそういうの上手じゃないですか。
と、「じゃないですか論法」を駆使して、帰国中の彫刻家と食事をしながら主張したのですが、上手じゃないよ、何言っているの、と返答されました。そうか、上手じゃないのか。
+ + +
そんな日常を送りつつ、ありがたいことに生活クラブの月刊誌『生活と自治』から、「修理する権利」についての取材を受けました。11月号に掲載されるとのことなので、もうこれね、ぜひ楽しみになさってください。涙あり、冒険あり、裏切りと命がけの友愛、そういったもののすべてがそこにないならないですね。でも編集者さんとカメラマンさんがとても素晴らしい特集にしてくださったので、ほんとうにありがたいです。喋っているところを写真に撮られましたが、いや撮られたというと変ですね、撮ってもらったのですが、ぼくではないみたいに良い雰囲気で写っています。何か良い人っぽい!
撮影担当でいらしたのはプロの写真家。魚本勝之さん。ちょうどいま川崎で展覧会をやっていますので、機会があればぜひ観に行ってください。
https://imaonline.jp/news/exhibition/20250824/
残念ながら埋め込みがうまくいきませんが、ぜひ上記のリンク先をご覧ください。「本の肖像」というタイトルの展覧会で、街中その他で本を読んでいる人びとが写されています。それぞれにとても良い写真です。取材を受けた後に少しお話をお聴きしたのですが、撮影の背景とか、とても興味深かったです。人を撮れる(単に写すというだけではなくその物語まで写しこめる)というのは、ほんとうに凄い才能です。
追記:魚本さんご自身によるステートメントがとても良かったので以下にコピペします。
本を読む、という行為に惹かれた市井の人々の肖像です。彼らが人生で最も影響を受けた本のタイトルと共に提示しています。それにより一人ひとりの肖像がより奥行きのあるイメージに昇華していきます。
上記サイトから引用
本は人の像を形づくる細胞であると信じています。
+ + +
そんなこんなで、何とか生きています。普通のことができません。昔から驚くほどそうなのです。自分でも毎日びっくりしているので、それはそれでお得な人生なのでしょう。だけれども、そういうことも含めて、ぼくという人間を駆動している魂のようなものが、七転八倒してそれでも何とか普通に生きているその滑稽でコミカルな姿を見おろして喜んでいるのを感じます。
たまたまデータの整理をしていたときに、昔々の写真やテキストが出てきました。変わっていないな、と思います。何も進歩していないというのは、良いことなのか悪いことなのか。いずれにせよ、自分の生きてきた軌跡というものが、まあだいたいダメ人間っぽくて滑稽だよねというのは……。やっぱり、良いことなのだと思います。せっかくなので、幾つかご紹介を。
わしらプレーリードッグは、昼になるとみんなのーんびり穴から顔を出してお日様を浴びるのが好きでな、何百年もそうやって暮らしてきた。ところがある日、ピコピコ鳴るハンマーでわしらの頭をぽこんぽこん叩くやつが現れた。叩かれたわしらはびっくりして気を失う。取って喰われるわけじゃないが、そのまま一晩経って風邪を引く連中が続出じゃ。そこでわしらは相談して、相手の裏をかくように、交互に頭を出すようにした。そこまでして巣穴から頭を出さなきゃならないのかと言われれば、まあそこがそれ、生き物の悲しい性というやつじゃ。それに誇りの問題でもある。だが敵もさる者、反射神経を磨き、わしらの先を読むようになった。プレーリードッグなのにいたちごっこ。プッ。いや失敬。とにかくそうやって、わしらと奴の戦いはいつまでも続いたんじゃ。お前さんがモグラ叩きとか呼んでるゲームには、そもそもモグラじゃあなくプレーリードッグの、こんな悲しい歴史があるんじゃよ。
遥か昔に書いた超短編。こんな話が無限にハードディスクから出てきます。何じゃこりゃ。
ペットショップで買ってきたばかりの彼は巣箱からぼくにそう語ると、餌をもぐもぐと食べ始めた。けどな爺さん、あんた、プレーリードッグじゃない。ミーアキャットなんだぜ。

いつか自分の人生を振り返ったときに、こういうわけ分からんもんがたくさんあった人生って……やっぱり、豊かじゃないですか(「じゃないですか」論法)。