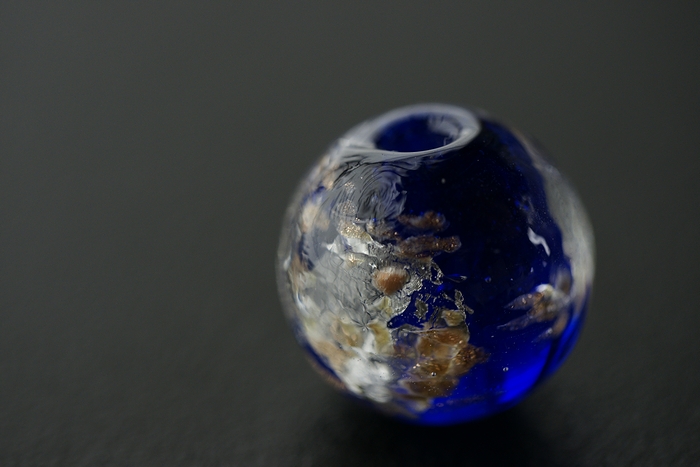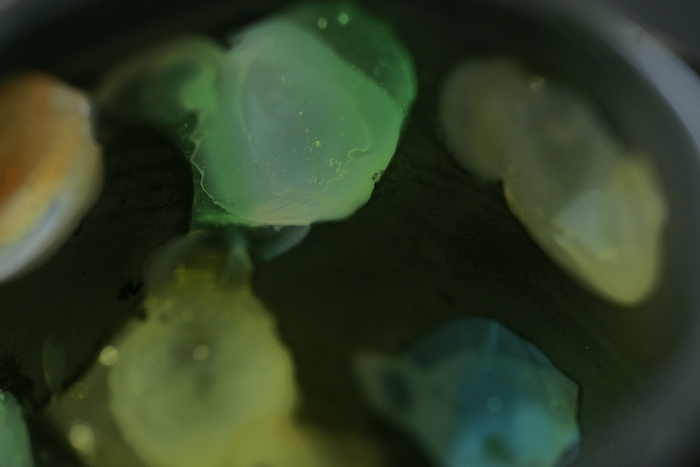ここ数か月、帰りの電車がいつも「××行き最終」とか、そんなふうになっている。よく働いている。他にやることがたくさんあるときに限って仕事も忙しくなる。けれども、こういった下らない忙しさがぼくのリアリティを支えているとも思う。彼女に会う時間が制約されるのは困ったものだけれど、それは残業で手に入る泡銭と気合と根性とストーカー紙一重の粘着気質でどうにかフォローする。そのほかのことは、基本、諦める。
それでも、先日、ひさしぶりに会社を早く上がり、八重洲ブックセンターに立ち寄った。最近は休日に東京に出るにしてもoazoの丸善に行くことが多かったので、ブックセンターはひさしぶりだ。oazoができる前は、三越前から歩いて丸善、明治屋、ブックセンターというのが散歩のお決まりルートだったけれど、どうしてだろうか、いまの日本橋丸善には、それほど魅力が感じられない。oazoの丸善だって似たようなものだけれど、結局、利便性を考えるとそちらになってしまう。明治屋も休業してしまった。
ともかく、八重洲ブックセンターだ。帰りに読む本が欲しかったので、一階の文学をうろうろした。昔とはやはりだいぶ本の並びが変わっている。海外SFの棚が縮小されたように感じる。幻想文学の棚にはバロウズがやけにたくさんある。ぼくが大学のころには、何だかちょっと格好をつけて(どう格好がついていたのかは知らないけれど)バロウズなんてよく読んだけれど、いま思えば、バロウズは空っぽで、文学的な価値などほとんどない。まあ、それはそれで、別に誰も困らないのだろう。
無駄なお金、ということでいえば、そもそもお金自体が無駄なものだ。高いハードカバーを買う気にならなかったのは、だから、その大きさと重さに耐え得るだけの魅力を持った本が見つからなかったからに過ぎない。心惹かれる本は、そもそも、既に持っているか読んだことがあるものばかりだ。結局、五階の文庫本のフロアに行き、村上春樹の東京何とかという短編集を買った。
村上春樹には興味がない。悪く言っているのではなく、単純に趣味ではないというだけだ。けれどいま参加している同人誌で村上春樹のある短編を読まなければならず、ぼくは意外にまじめなので、この機会に他の作品も読んでみようかと思った。内容は、やはり趣味ではなかった。ぼくにとってはバロウズ程度の意味しかなさそうだ。それでも、帰りの電車のなかをやりすごすには十分役立った。
外の世界は、まあ、だいたいにおいてハードすぎる。年をとるにつれて、それはどんどんきびしくなっていく。けれども彼女以外の誰に言っても、「きびしくなるね」というそのほんとうの意味は、伝わらない。
* * *
もうだいぶ前、彼女と、とあるホテルに泊まった。運よく部屋をグレードアップしてもらえ、ぼくらには分不相応な部屋に案内された。そこにはバルコニーのようなスペースがあり、こっそりふたりで頭を覗かせると、ロビーフロアを見下ろすことができる。広くて調度品も高級な部屋のなかも、自分たちの人生には何も関係がないという意味ではフィールドワーク的な面白さがあったけれど、その何もないバルコニーにこっそり隠れ、コンビニで買ったお菓子をもぐもぐもぞもぞと食べていると、何だか莫迦ばかしくも面白く、ふたりでくすくす笑っていた。