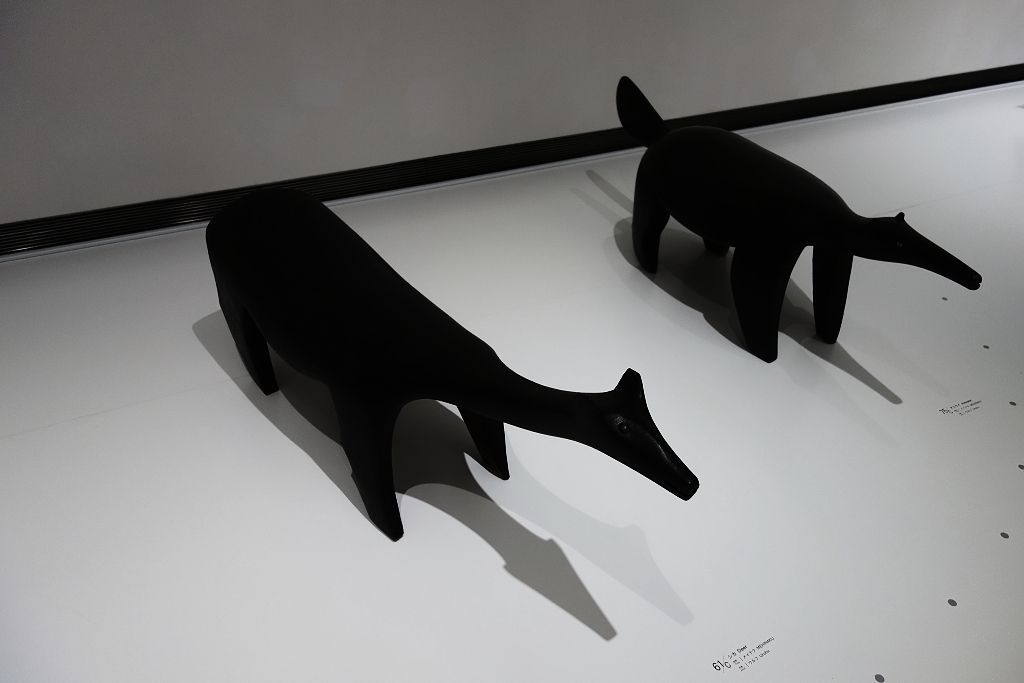仕事帰りにいま住んでいる町を歩いていると、時折ケーキを買うことのあるケーキ屋さんがまだ開いていました。もうそれなりに遅い時間なのですが、そういえば以前、ガラス扉に書いてある営業時間が長いことに驚いた記憶があります。最近、毎週金曜日の夜には、彼女とふたりで「生き残った記念日」を開催しているので、きょうはケーキを買って帰ろうと思い、お店に入りました。そのお店はもうだいぶお年のご夫婦が営んでいるのですが、きょうはおじいさんが店番です。うーん何にしようか悩みますねえ、などと話しながら選んでいると、おじいさんがぼくに、曇っていますか? と尋ねてきました。そういえば、遥か遠く海沿いの工場を出たとき、もう真暗で、月と星がきれいだったのです。だからぼくはおじいさんに、いや、曇っていませんね。ここの空は見上げなかったので分かりませんが、私の職場の方はきれいに晴れていましたよ、と答えます。するとおじいさんは笑って、いえ、ショーケースのことです、といいます。なるほど、ショーケースは一部が水滴で曇り、ケーキの幾種類かはよく見えません。ぼくも笑ってしまい、笑ってしまい……、いえ、このお話、特に落ちはないのです。ぼくはケーキを二つ買って帰りました。
落ちがないまま、ぼくらの日常生活は続いていきます。ここ数ヵ月は原稿を書くという点では非常に厳しい環境にあり、新しい文章を書いているかというと、普段に比べると十分の一がせいぜいです。年を取るにつれ、雑事ばかりが増えていき、しかもそれは単なる雑事ではなく、布団越しの重いパンチのように徐々に気力と体力を奪っていくような雑事です。
それでも、同人誌仲間のひとりの人間関係のおかげで、この数ヵ月の間に、二つの美術館のミュージアムショップに、ぼくらの同人誌を置いてもらえることになりました。そのうちの一つには彼女とふたりで泊りがけで覗きに行き、あたかも無関係な人間のようなふりをしつつ、おや、素敵な同人誌だねえ、これは買わざるを得ないねえ、などと絶叫しつつ一冊購入し、売り上げに貢献してきました。
それからもう一つ、企画書を送った出版社に目を止めてもらえ、本を出せることになりました。ほんとうは叢書として企画していたものですが、研究仲間はそれぞれのタイミングもありますし、研究者としても出版社としてもそれぞれに独自のスタイルがあります。それが合っているところと出会えることになったので、叢書ではなくなりましたが、結果的にはお互いにとって良かったと思います。こういうのって、やはり縁ですし、僥倖です。
ぼくの本についていえば来年中には出版したいので、予定としては年末までに原稿を仕上げなければならず、冷静に考えるとかなりやばい状況のような気もしますが、今年の最後のころには新しい家の本棚の部屋ができているはずなので、お休みの日にはそこに籠って、ぼくが見るこの世界の在り方をじみじみ書いていこうと思います。
本というものは、いうまでもなく、独りで作ることのできるものではありません。良い論文を書けばそれが本になって、しかも良い本になって、とは、ぼくは考えません。そうであるのなら、それは原稿だけ剥き出しで電子書籍か何かにして、Amazonででも売れば良いのであって、かつ、それは決して悪いことではない。けれども、それはぼくにとっての本ではない。古いタイプの人間であるぼくは、本は、やはり紙であり匂いであり、デザインであり、重みであり手触りであり、フォントであり、余白であり、それらすべてです。ページを捲るときの音、それを読む環境、そのすべてです。筆者だけではなくそれを見いだした編集者、デザイナー、DTPの担当者、流通業者、書店の人も、いえもっともっとたくさんのひとたちすべてからなる途轍もない総体の焦点として、ある一冊の本は現れます。
そういう本を作りたいなあと思います。そうはいっても、結局のところぼくにできるのは原稿を書くことだけです。ロジカルなだけのものではつまりませんし、小説になってしまってもいけません。そのどちらでもありどちらでもないような世界を書くこと、あるいはそのように見えている世界を書き表すこと。そしてそれを伝えること。どこまでできるかは分かりませんが、哲学というのはだいたいにおいて喰っていくには向いていないもので、それならせめて、ぼくにとっても、一緒に本を作ってくれる人たちにとっても、そして何よりそれを読んでくれるひとにとっても楽しいものになってくれるよう、地道に書いていこうと思います。