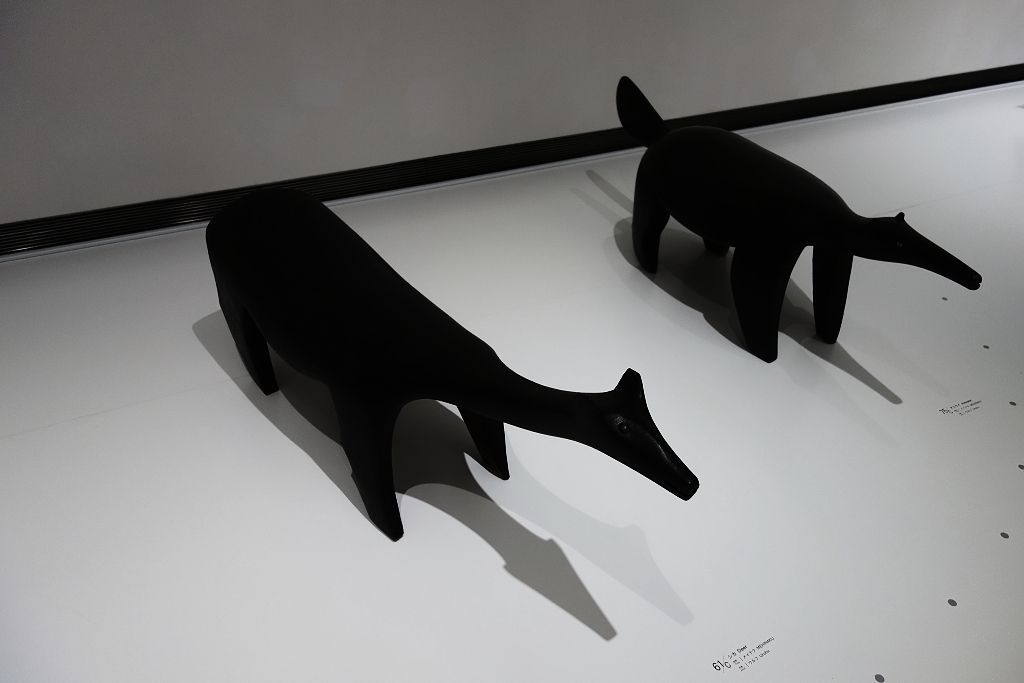もうきみがこんな話にうんざりしていることは十分承知しているけれど、また、家に「な」が出たんだ。昨晩、トイレに。だからぼくは、もう24時間近く手洗いに行っていない。水分はすべて汗で蒸発させようと、延々スクワットをする。汗くさくなり、お風呂に入りたいけれど、考えてみるとお風呂場なんて「な」の出現する危険性がいちばん高いところじゃないか。すべてがバラの香りとなって毛穴から出ていく銀河鉄道の夜の乗客でもあるまいし、何が何でも風呂に入らねばならぬ。だが入れぬ。思えばぼくの人生は「な」との闘争にのみ費やされてきた。すべて撤退戦だったけれどもね。――地獄ぢあ 地獄ぢあ、と、誰かが耳元で呟いている。だからぼくは、こんな世の中とはオサラヴァすべく、Oculus Goを買ったのさ。
+ + +
で、Oculus Goです。このブログ、ご存じのように何かのレビューとかできないししないので、特に使用した感想を書くというわけでもないのですが、でもまあ、子どものおもちゃだと思いました。良いか悪いかはともかく、基本的にそれ以上のものではありません。それでも、何しろぼくらが子どものころは想像もできなかったようなデバイスやコンテンツが2万円と少しで手に入るのですから、興味があるひとは手に入れても後悔することはないとは思います。とはいえ……その2万円というコストがほんとうに2万円なのか、ということに、ぼくらはもっと慎重になるべきなのかもしれませんけれども。
+ + +
ともかく、前にも少し書いたかもしれませんが、ぼくはVRというものは基本的にたいして評価していません。ですので、メディア論で論文を書くときも、原則、VRではなくAR、という立場で書いています。それは技術的な次元の話ではなく、造られたものと在るものの存在論的な差、ということです。その、在るものの変容こそを問う必要がある。
同じようにAIに対してもまったく評価を与えていません。あんなものはただの高速計算に過ぎない。とはいえ、だから凄い、ということも言えます。高速かつ大量かつ正確な、けれどもただの計算でしかない、というところにこそ、コンピュータが持つ凄まじいパワーの魔術性がある。そこにシンギュラリティだの知能だの、電通の戦略レベルにお粗末な話を持ってこられると萎える~、と思う訳です(ちなみに、MRに対しても、ぼくは電通的なコマーシャリズム以上のものを見いだせません。今後商業的にMRという名称が主流になっていくとしても、それは本質的な問題とは無関係だと思っています)。AIについては、また改めて書こうと思います。
ぼくは決して技術否定主義者ではありません。そもそもぼくの議論に対してそういう批判をしてくる連中の多くがまともにプログラミングすらできず、コンピュータの動作原理も知らずなので困ってしまうのですが、でも、所詮は技術なんです。そして「所詮」というのは、所詮人間に過ぎない、とか、ぼくらは所詮死ぬ運命にある、というのと同じで、そこには多くの意味が込められていなければならないものです。それが分かっていないなら、VRについてのメディア論の言説なんて、阿呆なものにしかなり得ない。現実も他者もそこに描かれないのであれば、VRは結局ただのスクリーン以上のものではないし、妄想の話をしたって、意味はありません。
+ + +
でも、「所詮」と同じく、「結局」だって、大したものかもしれませんよね。映画だって結局ただのスクリーンですが、ぼくらの人生に大きな影響を与えるような作品が幾らでもあります。もちろん、絵画や写真や映画とVRでは、根本的なところでまったく性質が異なっている。それは事実で、それが自分のいまの研究における――といってもここ三年がかりでやってきた研究であって、既にほぼ終息しつつあるものなのですが――重要なポイントになります。でも、ここではそのことはちょっと置いておいて、とりあえず共通点から考えると、その形式(写真や映画やVRヘッドセット)を突き破って、その向こうから現実や他者が現れてくるかどうか、ということが問題になってきます。
それがなければすべてはゴミだ、ということではありません。それにまた、現実や他者が現れるということは、政治的に正しくなければならないとか、現実の問題を扱わない娯楽作品は糞だとか、そういうことでもまったくありません。では何かといえば、それは端的に、意のままにならない、というところにあるのだとぼくは思います。圧倒的なリアリティというものの根本にあるのは、きっとこれです。自分の意のままにならない、という絶対的な直観。それが作品に命を与える。
+ + +
そういった意味では、実はARだって、現実なり他者なりに対して、意のままになるんだという幻想を、ぼくらに強烈に与える方向に機能することだってできます。商品としては、むしろそれが主なる意図です。VRだってARだって人間が生み出した技術だから、それは変わりません。でも、非常にざっくり言ってしまえば、造られたものと在るものの存在論的な差、というそのベースはまったく異なるし、その違いは無視できないものでしょう。それが、ぼくがARこそを議論の対象とする理由です。無論、ARの方が望ましい、ということではなく、その方がぼくら人間の在り方に本質的な影響を及ぼすだろう、ということです。VRは、まだ当分のあいだは、おもちゃにすぎません。
+ + +
でも、ひとつ、面白いアプリがありました。
“Notes on Blindness”というもの。このページに掲載されている紹介文をちょっと意訳してみます。
数十年に及ぶ恒常的な視力低下の後、1983年、John Hullは完全に視力を失いました。彼は自らの人生の激変を理解するための一助として、自身の経験をテープ上で文書化し始めました。このオリジナルの録音された日記は、失明に対する知識と情動に基づいた彼の経験の探究という物語の、新たな形式によるインタラクティブなノンフィクションというこの作品の基盤を成しています。
繰り返しますが、意訳です。そもそもぼくはフィーリングでしか英文読めないので。でも、この作品がとても良いのです。確かに映像は美しい。
 oculus goでキャプチャしたnotes on blindnessの一場面。実際にはもっと美しく、幻想的。
oculus goでキャプチャしたnotes on blindnessの一場面。実際にはもっと美しく、幻想的。
けれども、美しいだけであれば、それはただのビット情報に過ぎません。つまり、美しいということが表層的なイメージに終わるだけであるのなら。でもそうではない。あるとき、その向こうから現実が、他者が、イメージを突き破って圧倒的なリアリティとともに現れる。それがほんとうの意味で美しい。VRはぼくらにこことは異なる世界を体験させてくれるとか何とか、それはまあ、繰り返しますが、おもちゃとしてはそれで良いのです。でもほんとうの意味で異なるということであれば、それはどうしたって、このぼくの意のままにならない何者かがそこに在るからでしかあり得ないのです。そしてそうであるとき、VRとかARとか、そういった形式上の差異は、ほとんど無意味なものになっていくでしょう。
確かにVRでありつつもこことは別の、だけれども圧倒的な現実を描くことに成功している”Notes on Blindness”を眺めながら、そんなことを、改めて認識しました。何だか真面目な内容になってしまったな……。